「観念運動」は覚醒状態の人物の観念が身体運動となって現れる現象を指す言葉と言われています。
たとえば、接戦のサッカー試合のPKの場面になると、たった一人のキッカーが試合の結果の行方を背負うことになります。そうした場面で、「絶対にうまくやらねばならない。練習でも失敗することが多い。うまくいくだろうか」などといった想いが無意識下で自分を支配し、狙った通りのキックや作戦通りのキックが出せなくなってしまうようなことは、誰しもが経験しているか見知っていることでしょう。
催眠術師の多湖輝の著書『催眠術入門』には、観念運動の説明の部分で占い遊びの「コックリさん」も観念運動の一種であると述べられています。これも参加者のうちの1人の想い、または複数に共通する想いが、意識的ではなくても、指や手の筋肉の動きに現れて、起こる現象だと考えられると訳です。
催眠状態ではなくても、こうした観念運動によって無意識の想いが身体運動を支配したり身体運動に大きな影響を与えたりすることが分かります。
しかし、実践的催眠術の第一人者である吉田かずお先生は、観念運動という言葉を使ったことがありません。上で説明したような現象も広く催眠現象として考えるからです。吉田先生は催眠を催眠術師によって行われることだけとは考えず、変性意識状態の人物の無意識が暗示によって書換えられる現象はすべて催眠(現象)であると考えていました。
ですので、一般に言われる観念運動も自分が意識的に意図して起こしていないことではあっても、無意識下で行なわれる自己催眠の結果と考えることになります。上で挙げられているような事例でも、そこに関わっている人物は緊張状態で何かに集中する状況に陥っていると考えられますから、緊張系の催眠誘導の効果で変性意識状態になっていると考えることができます。
吉田先生はよく「鬱が酷くて『起き上がれない』とか『会社にどうしても出社できない』というような人には催眠暗示がとてもよく入る。なぜかと言うと、鬱も自己暗示の結果だから。催眠術師でもない人間が、自己暗示で起き上がれなくしたり、特定の場所に行けなくしたりする暗示を自分に受け容れさせているのだから、催眠術師の催眠暗示が入りやすいのは当たり前」と言っていました。
こうしたことも吉田先生の催眠の考え方、「吉田式催眠観」の特徴なのです。
☆参考書籍『催眠術入門 自分と他人の心を自在にあやつる心理術』
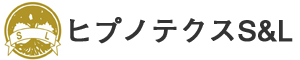
最近のコメント