「催眠についての関心は、洋の東西を問わず、最近、とみに高まり、医学や心理学における基礎的な研究もだんだん精緻になってきたし、その応用分野も急速に広がりつつある。しかし、これは他者催眠についての話であって、自己催眠となると、研究はかなり立ち遅れている。催眠の研究が最も進んでいると目されるアメリカにおいて、その傾向がとくに著しい。彼の国では、実験的研究や理論的考察が、ほとんどすべて、他者催眠について行われている。そのため、ときには、かなり偏った結果の考察や理論構成がなされているように思われるので、ニューヨークにおけるシムポジアムで成瀬はこのことを指摘しておいた。ことに催眠の性質を論ずるとき、他者催眠だけではどうしても充分でないので、自己催眠と併せ考えるべきだと強調した。」
これは日本の学術的催眠研究の大家成瀬悟策博士の著書(共著作)『自己催眠』の第一章の1に書かれている文章です。欧米を中心とする海外において、少なくとも他者催眠に比べる時、自己催眠の研究はあまり進んでいないと説明されています。
江戸末期から明治期に「催眠」という概念が紹介され、それが「催眠」と訳されるや否や、一気に日本全国に催眠の概念が広まっていきます。それはまさに他者催眠の概念でした。しかし、無心・無我・没我・沈潜などのそれ以前から日本にある言葉は、変性意識状態、つまり自己催眠状態を指している言葉で、禅や芸道・武道、各種の習いごとや作業の場面などで日本人の日常に息づいていました。
催眠という概念がもたらされると、それらが催眠の一種と括れることも理解されると同時に、明確な形式を伴って他者催眠の技術も国内に定着して行きました。しかし、まるでアントン・メスメルの辿った道のように、『魔睡』に見られるように女性への性加害の可能性が最初に取り沙汰され、医療技術の分野で医学との衝突が起き、千里眼や透視実験などで科学からも放逐され、戦争の恒常化に伴い軍を中心として国家そのものが催眠技術を独占して軍国主義浸透の手段となり、教育の分野からも締め出されて行きます。そのような流れは一柳広孝の『催眠術の日本近代』に詳しく描かれています。
取り締まる法律もでき、弾圧を受ける状態になった催眠は、霊術・気合術などと名前を変えて市井に浸透して行き、一部は新興宗教と融合して行きました。太平洋戦争前の段階でも、その施術内容は様々で技術レベルでは玉石混交だったと思われますが、全国で3万とも言われる霊術家が開業していたと言われています。
催眠と聞くと今でも如何わしいイメージをもたれることが多いですが、日本は歴史的に自己催眠を中心とした催眠技術を日常生活の中に採用してきた数少ない催眠大国だったのです。
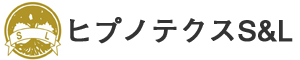
最近のコメント