SNSによって大流行になったMBTI診断が就職時にさえ活用されるようになったなどと言われます。初めて会った人間同士のコミュニケーションで最初にMBTIの型を名乗り合って、望ましいコミュニケーションパターンを展開し合うのも散見されます。
性格診断の手法は昔から多様です。無関係の血液型や星座による分類もありますし、心理学者が開発したものも古くはクレッチマーの気質分類からミネソタ大学による有名なMMPI性格検査などたくさん存在します。
催眠演芸で「あなたは犬になった」と暗示を入れると犬のようにふるまい始める…といった芸を見ることがあります。こうした芸は、あまり知られていない希少種の動物を指定すると、全く成り立たなくなってしまいます。人格を変える催眠技術も同様で、「(よく知っている)●●さんになる」は成立しますが、全く見ず知らずの人物は勿論、歴史上の人物なども断片的な知識しか持ち合わせていないと、催眠暗示でその人物にすることはできません。
米国で行なわれた或る実験で、そのような人格入替を成立させておいて性格検査を受検させたというものがあるようです。すると、元の本人の性格検査結果とは全く異なる結果が出ました。つまり、無意識の中には複数の性格分類が収められていることになります。これは最近耳にすることがある、「個人」に対する「分人」の考え方にも通じます。
人間は日常的に情報に曝され、経験を重ねていくうちに「学習」を重ね、無意識のプログラムもどんどん書き換わります。性格分類はインプットに対するアウトプットのパターンですから、それも「学習」によってどんどん書き換わり、古いものも消えずに記憶に保管されたままになることもあるでしょう。同一人物でもSNSではアカウント単位で性格が異なるでしょう。職場・家庭・友人づきあいなどの場面による使い分けも当たり前です。
このように考えると性格分類は固定的と考える方が難しいでしょう。一定期間だけ一定と考えることで性格分類が成立することがあるでしょうが、性格も移ろい変化するものであることが催眠技術の人格入替から分かるのです。
☆参考書籍『心は存在しない 不合理な「脳」の正体を科学でひもとく』
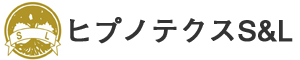
最近のコメント