1958年5月にハーバード大学医学部で開催されたシンポジウムで、センソリ・デプリベイションという呼称に統一された催眠手法は、それまで「隔離」、「知覚隔離」、「感覚刺激減弱」、「現実接触妨害」などさまざまな呼称があり、実際にその手法も様々なものが試みられていました。英語表現はSensory Deprivation で、日本語では直訳で「感覚剥奪」と呼ばれることが多くなりました。
人間は普段外界からの無数の刺激を五感で捉えつつ生活しています。その多くが止んでしまって、感覚的な刺激が激減した状態を作ることで催眠状態を作る手法が、このセンソリ・デプリベイションです。
一般に視覚と聴覚の刺激を減少させる手法がメインですが、視覚も全くの目隠し状態から、ピンポン玉を半分に割ったものを目に装着することで明かりだけは感じられるようにするなど、感覚遮断の程度にはバリエーションがあります。聴覚も同様で、全くの無音状態の部屋に閉じ込めることから、ヘッドフォンで一定の音を聞かせっ放しにする方法などがあります。
センソリ・デプリベイションの感覚遮断の度合いと時間長の、どのような組み合わせが望ましいのか、未だに明確な答えはなく、瞑想やヨガなどでも採用されている一方で、過度に長時間行われると、精神的が不安定になり、不安・幻覚などを引き起こす可能性が増大すると言われています。
元々は大学の研究施設や、軍部・諜報機関などの洗脳施設などで採用される手法で、個人が自己催眠として行なうようなものではありませんでしたが、日本の催眠研究の大家、成瀬悟策は、自律訓練法で有名なシュルツとの共著『自己催眠』の中で、センソリ・デプリベイションを取り上げ、自己催眠の手法の一つとして紹介しています。
たとえば、吉田式呼吸法など多くの催眠誘導手法は、明るくなく五月蠅くない環境で行なう方が圧倒的に望ましく、その意味では視覚・聴覚の刺激が少ない方が誘導を楽にできるのは、或る意味常識的です。その感覚の「剥奪」をもっと進めると、それだけで催眠誘導が働くようになる原理と理解することもできます。それであれば、他者催眠のみならず、自己催眠の手法としても相応に簡便な手法として認知されても良いように考えられるのです。
☆参考書籍『自己催眠』
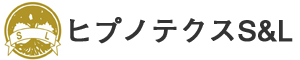
最近のコメント