2001年に発表された米コーネル大学のエプリーとダニングの研究が『自分を知り、自分を変える』と言う本に紹介されています。「来週行われる大学のチャリティで花を買うか」との問いを学生にしたら、「自分は買うだろう」と答えたのは83%でした。一方で「ほかの学生は花を買うと思うか」と尋ねたら、56%の学生が「買うだろう」と答えました。
実際に花を買った学生はたったの43%で、買うか否かの自己評価と、他者評価の結果を比較すると、明らかに他者評価がより正確であることになります。『自分を知り、自分を変える』の著者、ティモシー・ウィルソンは他の関連実験結果も紹介しつつ、これが事実であると述べます。
実質的に人間の行動や判断をほぼすべて司っている、現代的定義による無意識を、彼は「適応的無意識」と呼んで、フロイトが考えていた無意識と区別しています。そして、「人は、多少とも他者の適応的無意識から生じる行動に注意を向けているようだ」と述べています。
意識が単一システムで、一つずつの物事を時間をかけて判断処理していくのに対し、適応的無意識はリアルタイムで超高性能の多重処理システムで、意識がカバーしていないことに全部対応しています。意識が認識している自分はほんの一部であり、適応的無意識の膨大な処理結果全体を見ることができるのは他者であることは、考えてみたら当たり前です。
たとえば、「面と向かって人に話そうとすると、どぎまぎして仕方がない」と言うのは、よくある催眠施術の相談テーマです。そんな相談をする人が、実は周囲から見たら、十分話せている可能性も否めません。自己認識のいい加減さは、催眠施術上の最大の障害かもしれません。
☆参考書籍『自分を知り、自分を変える―適応的無意識の心理学』
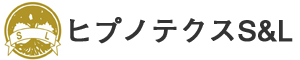
最近のコメント