江戸時代の臨済宗の禅僧である白隠禅師が70代になってから書いた『夜船閑話』に登場する「軟酥の法」という自己催眠による健康法があります。白隠禅師は本名白隠慧鶴で、1685年の生まれと伝えられています。多くの書画を残し、俳人としても知られ、広く民衆に禅宗の教えを広めた人物です。
「軟酥の法」は元々自分が患った禅病を癒すために1710年に白幽子という仙人から学んだものだと言われています。禅病というのは座禅などの修行を行ない続けることで、幻聴、幻覚、妄想、うつ病、自律神経失調症などの症状が発生することです。
軟酥は柔らかい酥という意味です。酥は本来「油で揚げるなどしたサクサクとした食感の食品」を指すことが多いようですが、同じ読みの「蘇(そ)」と混同した用法もあったようです。「蘇」の方は古代日本の乳製品の一種で、牛乳を煮詰めて作る製法が平安時代の書物にも登場する、練物的な食品群です。白隠禅師が言う「軟酥」が後者の方です。
『夜船閑話』の該当部分は、概ね以下のような説明で始まります。
「色も奇麗で香り高い仙人の神薬を各種煉り混ぜて、鴨の卵の大きさに丸めた丸薬が頭の上にのせてあると想像する。その軟酥の卵は、しばらく頭上にのせておくと体温で徐々に融けて流れはじめ、頭から垂れて流れ始めると具体的にイメージする。」
つまり、白隠禅師の言う軟酥は、柔らかに融けかかっているチーズやバターなどのイメージに近い状態の万病に効く架空の丸薬でしょう。それがドロドロと融けて頭部から体に染み込んでいき、最終的に体内全体に沁み渡って行き、足先にまで至るとイメージして行くのです。神薬が頭や体に染み込むのですから、心の問題も身体の問題も合わせて解消して行くことになります。
自身の身体の各部に順次意識の集中ポイントを移行させていく自己催眠法(/瞑想法)は類例が仙道や気功、ハタヨーガ、チベット密教のヴァジュラサットヴァ瞑想などにも見つかると専門書には説明されています。
吉田かずお先生の吉田式呼吸法も呼吸を整えて体を弛緩させつつ、自身の身体の各部ごとに脱力をイメージする方法で、自己催眠にも応用が可能です。乱暴にまとめれば、自律訓練法の6段階の公式も同様と考えることができるかもしれません。このように考えると、「軟酥の法」は具体的なイメージを用いた自己催眠による優れた治癒法であることが分かるのです。
☆参考書籍『白隠禅師—健康法と逸話』
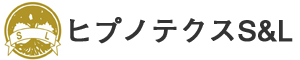
最近のコメント