高名な催眠技術の研究者であった成瀬悟策博士らによる『自己催眠』の中に、米国の精神医学医のエドモンド・ジェイコブソンによって提唱された漸進的弛緩法が詳細に説明されています。
催眠状態は“意識的な働きが抑制され心が弛緩している状態”と見ることができます。しかし、催眠誘導において「心を弛緩させてください」と言われても何をどうすれば良いのか分かりません。そこで心身の状態は一致して行くという原理を用いて、心ではなく体の方を弛緩させることで、心も結果的に弛緩して催眠状態になるのです。
しかし、今度は「全身から完全に力を抜いてください」と指示されても、なかなかできるものではありません。そこで漸進的弛緩法では2つの原理を採用することで、これを実現できるようにしています。その2つは「全身全部を一気に脱力するのではなく、一部ずつ脱力する」と「脱力ができるよう一旦力を入れて筋肉を収縮させ、その収縮を解いていく形で脱力を実現する」です。
簡単にまとめてしまうと、「普段の状態から脱力を目指すのは大変なので、身体の主要な筋肉のここに力を入れて力を入れた緊張状態を確認してからそれを脱力させることを、順次進めて全身脱力に至る」ということです。
『自己催眠』には「臨床的にも、骨格筋を十分に弛緩させると、内臓筋も同様に弛緩する傾向がみられる。だから、随意筋の弛緩によって心臓(※)や動脈などを含む内臓(※)系の間接的なコントロールができるようになるとされる。また、これによって、大脳皮質を安静化し、精神的な安静状態をもたらすことができるとされている。」と書かれており、漸進的弛緩法の原理を説明しています。
緊張させては弛緩に至る対象の筋肉は「収縮感のはっきりしている大きい筋群からはじめるのがよい」と書かれていて具体的な筋肉の名称なども『自己催眠』には列記されています。
吉田式呼吸法では緩慢な呼吸により脱力を全身に促しつつ、全身の部位を個別に徐々に脱力していく暗示を加えて行きます。個々の筋肉に力を入れてその収縮感を確認させるというプロセスはありませんが、「身体から力を抜くことで催眠誘導を行なうこと」や「脱力は体の個々の部分から行い全体に至ること」などの特徴は共通していると考えることができます。
吉田式呼吸法は吉田かずお先生のオリジナルの誘導法ですが自己催眠にも応用が可能です。ジェイコブソンが漸進的弛緩法を提唱したのは1920年代初めと言われていますので、先生の呼吸法案出の際の主要な先行事例となった可能性は高いように思えます。
※書籍中では「蔵」の字が使われているが、誤植と考えられるので「臓」とした。
☆参考書籍『自己催眠』
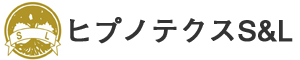
最近のコメント