イメージ・トレーニングについて脳の研究が進むにつれていろいろな事柄が判明しています。脳は実際にしている状態と外部のイメージを見ているだけの状態と脳内だけでイメージしている状態の区別をつけることが苦手なので、実際にしていなくても、トレーニング効果がイメージすることを通じて生み出すことができることが分かってきました。
イメージ・トレーニングは、スポーツなどの運動の分野以外でも、演奏などの音楽芸術の分野や、演劇などの体全体を使った演技の分野など、いろいろな場面で使われています。ビジネスの分野でも、営業活動の成功イメージを何度も反芻するようなトレーニングは以前からよく聞かれますし、職人の技などを伝授する際にも、教わる側が何度もリアルに見ては、そのイメージを反芻して身に着けるような場面はよくあります。
イメージ・トレーニングはスポーツや病気やけがによる運動機能回復など、体を理想的な形で動かす分野で特に研究が進んでいます。たとえば一人称イメージ(筋感覚性運動イメージ)と呼ばれる自分自身が動くイメージと三人称イメージ(視覚性運動イメージ)と呼ばれる他人が動いているのを俯瞰するイメージとどちらがどのように効果があるかなど、様々な研究が為されています。
催眠は暗示という言葉やイメージの「プログラム」を無意識に書き込む技術です。吉田かずお先生の「美女催眠」のように、特定の役柄の女優のイメージを大量に観てインプットした状態の女性に、その役柄の人物になると暗示を入れると、本当に言動や思考までもがその役柄の人物のように変わってしまいます。
詳細は書けませんが、私もコピー元となる人物のコミュニケーション技術を催眠技術で比較的短期間に(コミュニケーション塾のような場で)習得者にコピーしたことがあります。元イメージのインプット作業の効率化、そしてその無意識内への固定度合い向上。そうしたことに催眠技術は非常に有効なのです。
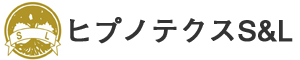
最近のコメント